ビジネスで目標設定をする際に「KPI」という単語を聞いたことがある人は多いと思います。
しかし、具体的にどんな意味なのか、KGIやOKRなどの似た用語と区別できていない人もいるでしょう。
そこで本記事は、KPIの意味やKGIなど他指標との違い、事例をもとに具体的な決め方、KPI設定を失敗しないコツを、わかりやすく簡単に解説します。
現在はデジタルマーケティング業界だけでなく、あらゆる業界において必要な指標となっているので、是非最後までご覧ください。
KPIとは

KPIとは、英語で「Key Performance Indicators」で、日本語にすると「重要業績評価指標」と翻訳でき、企業や各部門・個人が業績を上げるための目安となる数値目標のことです。
例えば、「今月の営業目標は30件」といった数値目標も、KPIのひとつと言えるでしょう。
KPIを設定することで、会社全体の目標を達成するために必要な動きが明確に把握でき、各部門のゴールとしてアクションを起こす指標になります。
また、KPIと関連した言葉として「プロセスKPI」という用語があります。明確な定義はされていませんが、各プロセスにおいて設定されるKPIのことを指すケースが多いようです。
例えば、ソフトウェア開発なら「要件定義」「設計」「開発」など、各フェーズでKPIを定めることにより、生産性を高める効果があります。
KGI・OKR・KFSとは
KPIと似た言葉にKGI、OKR、KFSといった用語があります。

KPIとの違いと、それぞれが使われる場面や事例について見ていきましょう。
KGIとは
KGIとは、「Key Goal Indicators」の略で、日本語にすると「重要目標達成指標」といいます。
わかりやすく考えると、「Goal」と書いてあるように最終的な目標を定めたものが、KGIです。
KPIは「パフォーマンス」を示す指標であるのに対して、KGIはより広い概念であり「最終的に企業が目指す目標」です。例えばKGIが「1年で2億円の売上を達成すること」であれば、それを達成するために「毎月2,000万円の売上をつくること」がKPIになります。
KPIは細分化されるため、KGIに対して複数のKPIを設定するのが一般的です。
KPIは「KGIを達成するために、プロセスの途中で進捗を確認するための指標」と考えるとわかりやすいでしょう。
OKRとは
OKRとは、「Objective and Key Result」といい、日本語に直訳すると「目標と主要な成果」に言い換えられます。
わかりやすくすると、OKRは複数の部門が持つ共通のゴールであり「会社全体で目指すべき目標設定」です。KGIも似た意味を持ちますが、OKRは「達成できそうな目標」で、OKRを達成することで企業の成長を促す目的も含まれます。
一方、KGIは「必ず達成するべき目標」であり、OKRを達成する手段のひとつといえます。例えば「業界の4割のシェアを持つトップメーカーになること」は、OKRに定められるでしょう。
近年の日本ではメルカリやサイバーエージェントなどの、成長企業も取り入れているフレームワークであるため、今後ますます注目されるでしょう。
KSFとは
KSFは「Key Success Factor」の略で、直訳すると「重要成功要因」といいます。簡単にいうと、KPIやKGIを達成するために必要な重要項目のことです。
例えば、インターネット回線を例にとると「エンドユーザーに長期で利用してもらうこと」が売上につながる大きな要因(KSF)です。そのために、契約満了前に新プランを提案したり、付加価値があるサービスを紹介したりするなどのアクションを起こす必要があります。
このようにKSFを分析することで、より具体的なアクション項目を洗い出すことが可能です。
同じ意味として、CFS(Critical Success Factor)という用語がありますが、意味はKSFと同じであり、大きな違いはありません。
KPIが導入される理由3つ
KPIを設定する理由はいくつかありますが、重要なものとしては公正な評価をするためや、企業が活動するうえで次のアクションを明確にするため、といった様々なことが挙げられます。
ここでは、KPIの重要性をいくつかの項目に分けて解説していきます。

公正な評価をするため
KPIを使う理由のひとつは、公正な評価をするためです。
KPIは、各部門に対してはもちろん、チームや個人にも設定するケースが大半です。
個人のスキルやパフォーマンスを数値で表すことにより、偏った考え方にならず客観的に公平に評価することが可能です。
また、社員に対してKPIを明らかにすることにより、公正に評価することを理解してもらえるメリットもあります。
自社の業績を可視化するため
KPIを使う二つ目の理由は、自社の業績を可視化するためです。
樹立した目標を数字に落とすことで達成率がわかり、もし達成率が低い場合は次のアクションを模索するきっかけになります。
定めたゴールに対して進捗を確認し、達成するための指標としてKPIは欠かせない軸(=行動指針)といえるでしょう。
やるべきことを明確にするため
KPIを使う三つ目の理由は、やるべきことを明確にするためです。
部門、課、チーム、個人ごとにKPIを設定することで何をすればいいかが明らかになり、日々の業務でのタスクが決まります。
KPIを軸にすれば、日々の業務内容が必然的に決まるため、次のアクションに迷うことがなくなるでしょう。
このように、KPIによって「業務を整理する」という考え方も押さえておきましょう。
KPIを効果的に設定している事例
実際に、企業で導入しているKPIの事例をいくつか紹介します。
インターネット回線の営業部門のKPI
インターネット回線の営業で、KPIに設定される主な項目は以下の通りです。
- 売上
- 受注案件数
- 利益率
- 解約率
- クロスセル成約数
営業部門の場合は売上や受注件数、利益率などがKPIの対象となるケースが多いです。
インターネット回線の営業では、長い年数利用してもらうことが前提となるので「解約率」も大切な指標のひとつになります。
コールセンター部門のKPI
コールセンター部門のKPI事例は、以下の通りです。
- 対応件数
- 対応時間
- 架電件数
- 応答速度
- 顧客満足度
コールセンター部門では、いかに素早く対応し、相手の意図をくみ取って対応するかが求められます。
物理的にかかった時間や対処した件数はもちろん、ダイレクトにユーザーとやり取りするので「顧客満足度」も重要な指標です。
失敗しないKPIの決め方
KPIを設定する際には、事前に知っておきたいポイントがいくつかあります。
データの分析をすることや数値化できる項目を使うこと、あらかじめKGIを設定することなどを意識したうえで、失敗しないKPI設定をしましょう。

データ分析で仮説を立てる
KPIを決めるときの前提として、今あるデータを分析して仮説を立てることが求められます。
現在の状況を把握したうえで仮説を立てて、それを検証するのがKPIの役割でもあります。
例えば、サービスの購入もとを分析して、その中でインターネットからの検索流入が多いとわかったら「今後はSEO対策に力を入れるべき」という指標が見つかるかもしれません。
データを分析せずにKPIを設定すると、現在の状況からは達成不可能な目標ができてしまう恐れがあるので気を付けましょう。
数値化できる項目をKPIにする
次のポイントは、数値化できる項目をKPIにすることです。
当たり前ですが、ビジネスを進めるうえでは進捗を確認して、社内の担当者同士で共有することが欠かせません。
そのためにシステムやクラウドアプリを活用し、現状の達成率などを常に可視化できる体制を整えましょう。
営業部門であれば、SFA(営業支援システム)などの管理ツールを使うと良いでしょう。
実現可能な目標を設定する
KPIは、目標が低すぎても高すぎても、その効果を最大限発揮できません。
今の状況を見て、現状より少し頑張れば達成できそうな数値を設定することが大切です。
例えば、営業数字であれば、去年の実績よりも「+5%前後」が主な目安になるでしょう。
「努力次第で達成できる」と思える数値にすることで、社員の達成意欲向上にもつながり、最終的なイメージをしやすくなります。
目標設定の順序を間違えない
KPIは、あくまでもKGIがあってこその指標です。
まず企業全体で何を目指し、どのようにビジネスを展開させていくのか明確にしたうえで、細かな部分を数字に落としていきましょう。
解像度を段々と上げていくイメージで「OKR→KGI→KPI」の順番に設定し、それに付帯してKFSを決めていきます。
全体の軸があってはじめてKPIを決められるので、まずは大枠から固めることを意識することが大切です。
KPI達成の鍵は「OODAループ」
KPIをはじめ、KGIやOKRを達成するためには、OODAループを回して常に軌道修正できるようにする仕組みが大切です。
従来の営業活動においては、PDCA(計画・実施・評価・改善)サイクルが重要な枠組みとされてきましたが、新しいフレームワークとして「OODAループ」が注目されています。

これは、「Observe(観察)」「Orient(仮説)」「Decide(意思決定)」「Act(行動)」の4つのから成るサイクルで、同じ方向に進めるだけでなく、時には前のステップに戻して回すこともあるため、「ループ」と呼ばれています。
PDCAサイクルよりも、意思決定と行動の高速化を促し、変化への対応力をあるため、KPIやKGIの運用に最適です。
- Observe(観察)
顧客の購入ルートを探ると、インターネットからの検索流入が急増していた - Orient(仮説)
SEO対策により力を入れるべき - Decide(意思決定)
┗ 新規記事を〇月までに○○記事作成する
┗ 既存記事のリライトを外注する - Act(行動)
┗ SEO部門の人員を増やして実行する
┗ 外注先を探して決める
まとめ
今回はKPIとは何か、他の用語との違いや具体例、設定時のポイントなどを解説しました。
KPIは企業活動をするうえで欠かせない指標であり、目標を達成するためのロードマップでもあります。
正しいKPIを設定すれば業績アップにつながりやすくなるので、ぜひ今回紹介した考えを取り入れてみてください。

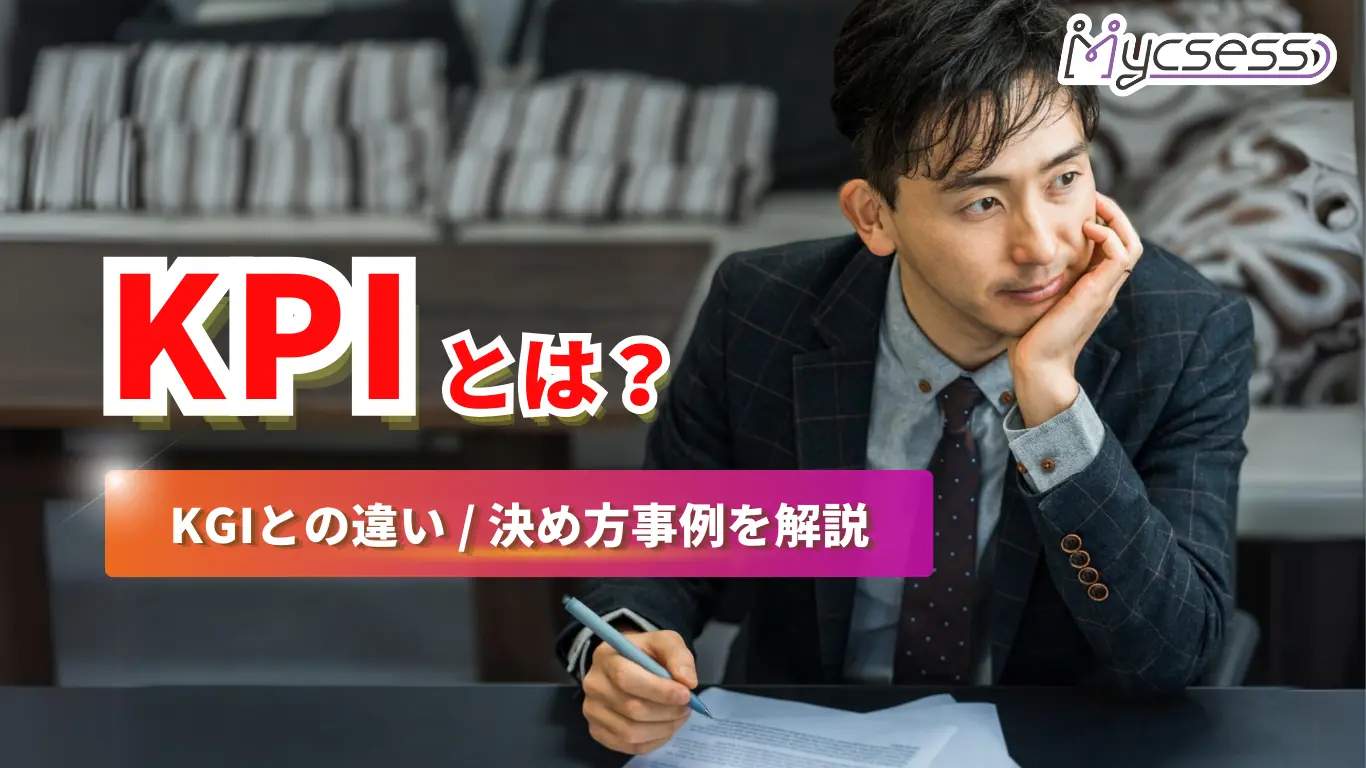









コメント